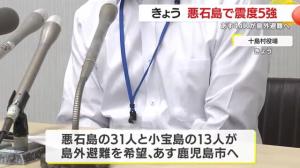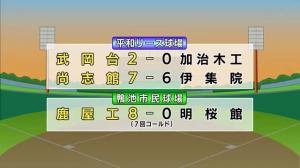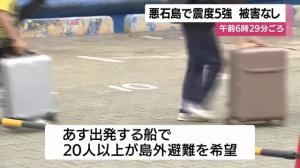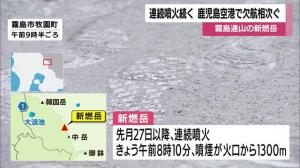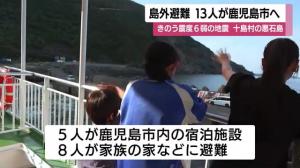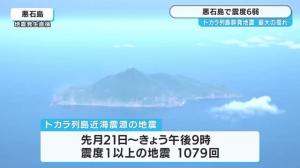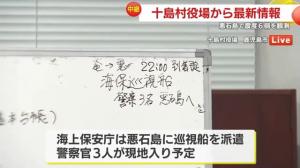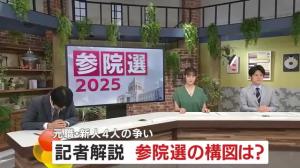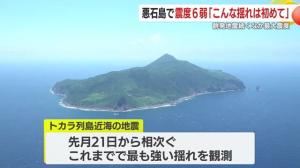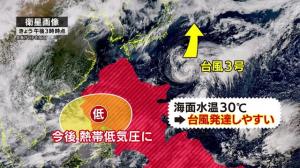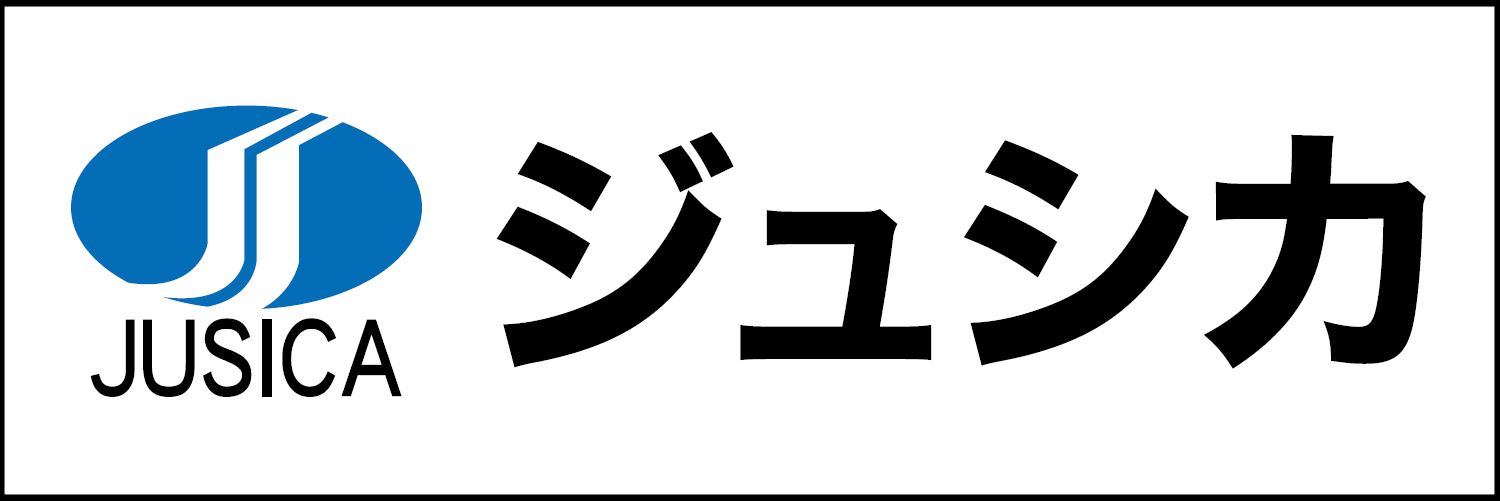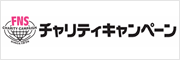【鹿児島・奄美群島日本復帰70年】奄美の人々の食を支えた植物「ソテツ」
2023年12月27日(水) 13:00

奄美群島の日本復帰70年を見つめるシリーズ企画「奄美を想う」。今回は当時の食生活を振り返る。
アメリカ軍の統治下で困窮した奄美の人々の食を支えたのは、南国に自生する植物「ソテツ」だった。赤い実には毒があるが当時、人々は手探りで毒抜きを行い、なんとか空腹を満たしていた。
「ソテツ」は九州南部より南に自生し、奄美大島・龍郷町の群生地では圧巻の光景が広がる。ソテツは秋から冬にかけて赤い実をつけるが、「サイカシン」という毒を含んでいて、口にすると呼吸困難になり、死に至ることも。
しかし、このソテツの実が、アメリカ軍の統治下で困窮する奄美の人々の命をつないだ。
終戦後、1946年2月にアメリカ軍の統治下に置かれた奄美群島。本土からの物資が届かなくなった奄美の人々は、食べ物もない、貧しい生活を強いられた。
当時の奄美の暮らしぶりを伝える映像には、茶わんに盛られたソテツのおかゆをすする光景が記録されている。そして「ソテツを常食としていた」とのナレーションが。
奄美市笠利町の和田昭穂さん(91)にソテツの毒をどのように取り除いていたのか教えてもらった。
奄美では「ナリ」と呼ばれているソテツの赤い実。「ナリ」を半分に切り取り、出した白い実の毒を抜く。
和田昭穂さん(91)
「川の水に1~2週間ほどさらすんですよ」
水にさらす期間に根拠はあったのか?
Q、1週間くらいつけないと毒は抜けない?
和田昭穂さん「抜けたか抜けないか分からない。分からないけれども、抜けただろうということで昔はみんな勘ですよ」
毒が抜けたかどうかも分からないソテツを食べて、当時の人たちは統治下のひもじさをしのいだ。
奄美市で郷土料理店を営む恵上イサ子さんは昔の料理の研究もしている。ソテツをおかゆにする当時の手法を再現してもらった。
毒抜きしたソテツの粉を水に溶かし、さらに何度も上ずみ液を捨てる。
なつかしゃ家・恵上イサ子さん(73)
「ナリガイ(ソテツのおかゆ)にするまではこの工程を5、6回する。毒をもっともっと消そうという人たちの知恵だったのかなと思う」
その作業が終わると液体を沸騰したお湯に注ぐ。
なつかしゃ家・恵上イサ子さん
「これがだんだん固くなっていく。デンプンなので。ナリが生なので火をきちんと通すということが(大切)」
20~30分ほど煮詰めとろみがついたら完成。
当時、和田さんは二十歳前後の食べ盛りだったが、ナリガイは決しておいしいものではなかった。和田さんも次のように振り返る。
和田昭穂さん(91)
「昔は乾燥する時間が長くて。しかもここは多湿だから黒いカビが生える。それで『ナリガイ』と言えば『臭いがあるもの』」
県外で教師として働いた後、奄美大島に戻ってきた和田さん。2009年に工房を立ち上げ、ソテツの商品化を始めている。
和田昭穂さん(91)
「(ナリガイは)貧しいという気分が先にくる。それで臭いがするだったら私は今度作る時に、臭いをまず取ろうと。ソテツの本当の味はこんなものだよというのを知らせたい」
その思いで、誕生したのが「ナリ粉」。毒抜きしたソテツの実を乾燥機で乾かして臭いを抑え、粉末にたもの。奄美大島のスーパーなどで市販され、片栗粉のような用途でも使われている。
和田昭穂さん(91)
「貧しい思いをしてソテツを食べたから「ソテツに恩返しをしよう」と。私だけだろうと思うけど。「(ソテツを)残しておきたいな」と」
統治下で人々の命をつないだソテツ。日本に復帰して70年が経つ現在も、あのときの記憶を奄美に伝えている。
アメリカ軍の統治下で困窮した奄美の人々の食を支えたのは、南国に自生する植物「ソテツ」だった。赤い実には毒があるが当時、人々は手探りで毒抜きを行い、なんとか空腹を満たしていた。
「ソテツ」は九州南部より南に自生し、奄美大島・龍郷町の群生地では圧巻の光景が広がる。ソテツは秋から冬にかけて赤い実をつけるが、「サイカシン」という毒を含んでいて、口にすると呼吸困難になり、死に至ることも。
しかし、このソテツの実が、アメリカ軍の統治下で困窮する奄美の人々の命をつないだ。
終戦後、1946年2月にアメリカ軍の統治下に置かれた奄美群島。本土からの物資が届かなくなった奄美の人々は、食べ物もない、貧しい生活を強いられた。
当時の奄美の暮らしぶりを伝える映像には、茶わんに盛られたソテツのおかゆをすする光景が記録されている。そして「ソテツを常食としていた」とのナレーションが。
奄美市笠利町の和田昭穂さん(91)にソテツの毒をどのように取り除いていたのか教えてもらった。
奄美では「ナリ」と呼ばれているソテツの赤い実。「ナリ」を半分に切り取り、出した白い実の毒を抜く。
和田昭穂さん(91)
「川の水に1~2週間ほどさらすんですよ」
水にさらす期間に根拠はあったのか?
Q、1週間くらいつけないと毒は抜けない?
和田昭穂さん「抜けたか抜けないか分からない。分からないけれども、抜けただろうということで昔はみんな勘ですよ」
毒が抜けたかどうかも分からないソテツを食べて、当時の人たちは統治下のひもじさをしのいだ。
奄美市で郷土料理店を営む恵上イサ子さんは昔の料理の研究もしている。ソテツをおかゆにする当時の手法を再現してもらった。
毒抜きしたソテツの粉を水に溶かし、さらに何度も上ずみ液を捨てる。
なつかしゃ家・恵上イサ子さん(73)
「ナリガイ(ソテツのおかゆ)にするまではこの工程を5、6回する。毒をもっともっと消そうという人たちの知恵だったのかなと思う」
その作業が終わると液体を沸騰したお湯に注ぐ。
なつかしゃ家・恵上イサ子さん
「これがだんだん固くなっていく。デンプンなので。ナリが生なので火をきちんと通すということが(大切)」
20~30分ほど煮詰めとろみがついたら完成。
当時、和田さんは二十歳前後の食べ盛りだったが、ナリガイは決しておいしいものではなかった。和田さんも次のように振り返る。
和田昭穂さん(91)
「昔は乾燥する時間が長くて。しかもここは多湿だから黒いカビが生える。それで『ナリガイ』と言えば『臭いがあるもの』」
県外で教師として働いた後、奄美大島に戻ってきた和田さん。2009年に工房を立ち上げ、ソテツの商品化を始めている。
和田昭穂さん(91)
「(ナリガイは)貧しいという気分が先にくる。それで臭いがするだったら私は今度作る時に、臭いをまず取ろうと。ソテツの本当の味はこんなものだよというのを知らせたい」
その思いで、誕生したのが「ナリ粉」。毒抜きしたソテツの実を乾燥機で乾かして臭いを抑え、粉末にたもの。奄美大島のスーパーなどで市販され、片栗粉のような用途でも使われている。
和田昭穂さん(91)
「貧しい思いをしてソテツを食べたから「ソテツに恩返しをしよう」と。私だけだろうと思うけど。「(ソテツを)残しておきたいな」と」
統治下で人々の命をつないだソテツ。日本に復帰して70年が経つ現在も、あのときの記憶を奄美に伝えている。